 |

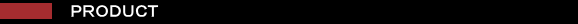
 |
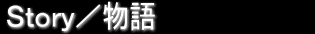
ミケロッティ・ヒストリー
ジョヴァンニ・ミケロッティはその飽くなき探究心から、大メーカーやカロッツェリア、果ては裕福な個人オーナーの求めにも応じて、美しいボディラインを次々と創造した。彼がデザインしたクルマが放つ強烈な存在感は、都市背景のひとつにさえなり、現代に至るまで自動車の美的感覚を決定づけるほどの影響力を保ち続けている。
ジョヴァンニ・ミケロッティ(1921-1980)は、その生涯におよそ3500車種の自動車のデザインを手がけたとされてる。もちろん、その全てが実現化したわけではない。しかしなたが、彼がイタリア自動車デザインの伝統を世界に轟かせたスタイリストの中でも、その第一人者というべき存在であることには間違いないだろう。
ミケロッティが自動車のデザインに強い興味を抱くようになったのは、彼がまだ子供時代の頃のこと。幼少期からやっかいな病気を患っていた彼は、ずいぶん大きくなるまで、周囲の子供たちのように外に出て遊ぶことが許されなかった。1937年、16歳に成長したジョヴァンニ・ミケロッティ少年は、まだ正式雇用ではない見習いデザイナーとしてだが、当時トリノでは一流と言われていたカロッツェリア・スタビリメンティ・ファリーナに採用されることになった。たとえ身体は弱いとはいえ、何らかの職には就かねばならなかったわけだが、幼少期から憧れた自動車デザインの現場に加わって、まずは取るに足らないパーツのデザインから命じられることになる。
ところが、ジョヴァンニは着任草々から驚くべき才能を発揮し、社主アッティリオ・ファリーナはすぐさま彼に正規デザイナーの地位と専用の製図台を提供して、それに応えるのであるこの時代のスタビリメンティ・ファリーナの。チーフデザイナーはピエトロ・フルア。そして、イタリア自動車デザインの父と言われる、マリオ・レヴェッリ・デ・ボーモン伯爵が外部コンサルタントとして協力し、溢れんばかりのアイディアとイノベーションを持ち寄り、ともに創造するという体制を採っていた。
ある日、アッティリオ・ファリーナは自分のオフィスにミケロッティを呼び、レヴェッリが走り書きしたアイディアスケッチを実行案として使用可能なデザイン図に描き起こすように命じられた。承知したジョヴァンニは素晴らしい速さでデザイン画を描き上げ、アッティリオに提出した。
ジョヴァンニ自身もそんなことをすっかり忘れていた数日後、この日出社していたマリオ・レヴェッリ伯爵は、自分のスケッチを実行案に移した優秀なデザイナーは誰かと訊いて回った。素晴らしい出来映えを自分の言葉で誉めてやりたい。伯爵はおそらくそう考えたのであろう。
そして、レヴェッリが引き合わされたのは、デザイン・テーブルの前で頬を紅潮させた、まだ年端も行かない半ズボン姿の少年だったのである。この日を境に、すでに巨匠と呼ばれていた老練デザイナーと、ほんの少し前まで見習だった新人デザイナーは無二の親友となった。そして、若きジョヴァンニ・ミケロッティは恩師マリオ・レヴェッリ伯爵から、そのすべてを学び授かったのだ。18歳を迎えてすでに独立した仕事も任されるまでに成長していたジョヴァンニは、アッティリオ・ファリーナとの意見の食い違い原因となって解雇されたピエトロ・アルファに代わって、スタビリメンティ・ファリーナのチーフ・スタイリストに抜擢されるにいたった。
こうしてチーフに昇格した若きミケロッティだが、ワンオフカーを求めるスタビリメンティ・ファリーナの裕福なクライアントと直接コンタクトを持つ機会を得て、後のキャリアに役立つ人脈もこの時期に開拓して行くことになる。第二次大戦が勃発する直前のヨーロッパには、まるで仕立屋に通うようにしてカロッツェリアに赴き、自動車のボディをオーダーメイドで製作させる裕福な階層が依然として存在していたのだ。
しかしその一方で、大衆向けの車をデザインする際には生産上の問題も避けて通ることはできず、より厳しい要求を突きつけられることもしばしばだった。ミケロッティはこの時期の経験から、ファンタジー性と合理性、そして先進のテクノロジーという重要な三つの要素をバランスよく調和させることが、自動車デザインの秘訣であることを学んでいる。
このデザイン哲学がその真価を発揮したのは、なにも車においてだけではなかった。戦時中の厳しい時期に彼が創作したもののなかに、小さな木炭ストーブがある。今となっては詳細は明らかではないが、当時世界で最も小さなストーブ(45×40×30cm)で、2口の火口と"かまど"を備えていたとされる。
戦争が終わると、ジョヴァンニはいよいよそのずば抜けた想像力を発揮し、新たなデザイン・トレンドの模索から、それを洗練させる活動へと重心を移す。
彼は個人的なプロジェクトとして、フェンダーをボディラインに統合させたモノリス(一体化)スタイルを研究し、ランチアのシャーシを利用して興味深い実験車両を製作した。そして、この習作をヴィラ・デステのコンクール・デレガンスに何台かのアルファロメオやフィアットとともに試験的に出品してみると、それらライバルを寄せ付けることなく、見事、優勝を遂げたのであった。
そんなこともあって、おびただしい数の熱狂的なオファーがスタビリメンティ・ファリーナに殺到し、同社内だけではボディのデザインから製作にいたるオファーを一貫してこなすことが困難になっていった。
そういう経緯もあってであろうか、1947年にはアッティリオ・ファリーナ自身の資金援助を受けたミケロッティは独立。カロッツェリア・スタビリメンティ・ファリーナをメインのクライアントとして第一次的に優先しながらも、スタビリメンティ・ファリーナに今度は外部から協力するという取り決めを持ったデザイン・スタジオを開設することになる。
この瞬間から若き転載スタイリスト、ミケロッティは、我と我の身の主となったわけだが、自分のアイディアを表現するためにはボディ設計者としても働かねばならなくなった。彼にとってプロジェクトの実行力とフレッシュな想像性の両立を、あたかもプロポーションのバランスのごとく重要なものとして考えねばならなくなった。
たとえ新しいアイディアが浮かんだとしても、まずは仲間たちとの間でもう一度可能性を検討し、それで実効性が確立されない限りは容易にゴーサインは出せない。もしダメな場合は、より良い新しいアイディアを模索する。しかし、そんな厳しい条件下にあろうとも、彼の創造力は新たなモチーフに富み、依然として安易な装飾には頼らなかった。そして、過去のいかなる傑作との比較にも十分耐え得るものであった。プロフェッショナルの目から見ても。彼の器量は特筆に価するほどに優れたものであった。
ミケロッティは注文主の意向やテクノロジーの著しい進歩に適応して、新たなラインを創造する能力も兼ね備えていた。
大メーカー向けにボディ・デザイン作業を請け負うときのミケロッティは、常に日頃、高級車の少数製作を担当している芸術家的デザイナーとしてではなく、近代的な工業デザイナーへと変貌してみせた。経済性や生産性、社会性から企業イメージ、そしてマーケッティングの結果など、成功する商品としての条件を充分に考慮した上でデザインするという、現在でも通じる術を身に付けていたのである。
事実、ミケロッティは、スタイリング開発から製図デザインにいたるまで、自動車デザインにおける全工程を一社でこなし、しかも過不足ない結果を残すことのできる、当時では数少ないデザイン・スタジオの一つだったのは間違いない。
創業当初は小規模のカロッツェリアやコンストラクターがおもなクライアントであった。
また、この時期にはヴィニャーレ-ミケロッティのコンビで、実に140台ものフェラーリ・ボディを架装している。そのなかの数台は、三度もにおよぶミッレ・ミリアでの優勝を始めとして'50年代の重要なレースで勝利の栄冠に輝いている。
ミケロッティはその後も飛躍的な成長を続け、1958年にはその最盛期を迎えていた。この年のトリノ・ショーには、彼がデザインを手がけたニューモデルが、数メーカーにまたがって、実に40台も出品されるに至ったのだ。それまではカロッツェリア向けの仕事が多かったのだが、この頃には逆転して、大メーカー向けにボディの構造設計まで引き受けるトータル・デザイン的なビジネスが大多数を占めるようになっていた。
これらの新しいビジネス・スタイルの端緒となったのが、ミケロッティがスタイリングの見直しを手がけ、盟友ヴィニャーレが新ボディを製作した、スタンダード"ヴァンガード"であろう。
このイギリスの大メーカーは彼らが提示した新しいボディ案を即座に生産することを決定し、同社とミケロッティとの間には『今後スタンダード及びトライアンフで開発される全ての新型車のデザインを委ねる』をいう契約が交わされることになる。
脂の乗り切った名スタイリストは、イギリスの新たな友人のために、英国的伝統主義とイタリアのフレッシュなスタイルを両立させたデザインに挑戦し、見事に成功させた。こうした背景で生み出されたトライアンフの"ヘラルド"や"スピットファイア"、"TR4"、"ドロマイド"、そして"スタッグ"などの製品は、イギリス国内ではなく、国際的にも成功を収めることになる。
また、同じ1958年にはBMWとの協力関係も、より深いものとなった。それまでに"イセッタ"のスタイルをBMW版のために手直しして欲しいとの依頼でミュンヘンに呼ばれたことはあったが、このときにはオリジナルのイタリア版から数箇所のライン変更を示唆するだけという簡単な作業に終わっていた。
しかし、その後に大型サルーンの"505"や、哀れなほどに醜かった"600"をベースとしていながら、スタイリッシュに変身させた"700クーペ"などを手がけ、数年来にわたる無骨なデザインで評判を落としていたBMWのスタイリングはおろか、この直前の時期には倒産の危機に瀕していたBMWの経営状態までもを見事に復活させたのである。
ミケロッティに恩義を覚える一方、再び自動車メーカーとしての自信を取り戻したBMWは、社運を賭けた新型サルーン"1500"のデザインもミケロッティに託した。果たして、この"ノイエ・クラッセ"も記録的な大成功を収めると、後に続く"1800/2000"、小型2ドアサルーンの先駆けとなる"1600"、久々の大型高級車"2500"や人気沸騰中の2ドアから派出したスポーツワゴンの"1602/2002ツーリング"、最高峰に位置する最もスポーティーな"3.0CSL"にいたるまで、殆ど全てのモデルでボディ・デザインを手がけることになる。
さらに同じ1958年、ミケロッティは日本の自動車メーカーと関係を結んだ最初のデザイン・スタジオにもなっている。フジ(注釈:のとにプリンス自動車工業となる富士精密工業のこと)がそのパートナーで、'60年11月に開催された第42回トリノ・ショーに出品されたプリンス・スカイライン・スポーツ"こそ、両者の提携の成果である。
この後、日本では日野自動車が"コンテッサ"クーペとセダンのデザインをミケロッティに委ね、市場でも満足すべき営業実績を残している。また、これからの世界的な成功に目を留めたオランダでも扉が開かれ、DAF社の小型サルーン"33"とそのバリエーション・モデルである"66"のデザイン作業を全面的に請け負うことになった。
ところが、こうして大々的に手を広げたプロダクション・モデルの仕事ではあるが、多人数のクライアントの満足を得るためには一定の節度を持ったものでなければならず、ミケロッティ自身のファンタジーや美的インスピレーションを刺激するようなデザインとはなり難かった。そして、ジョヴァンニ・ミケロッティ自身も感性も生産車のデザインばかりでは、ややもすると鈍る傾向があったのだ。すでに自動車デザインの都、トリノでも押しも押されもせぬトップ・スタイリストの地位にあったミケロッティだが、やはりヨーロッパ以外の国でも活躍できるような感性を養うには、一切の拘束のない環境で、自らの美的インスピレーションを開放する必要があったのである。
その目的を果たすために、ミケロッティは1960年頃から自らのブランド名のクルマを製作し始める。かつてスタビリメンティ・ファリーナの製図版で、特別なボディラインと熱望するごく少数のクライアントのためにデザインしていた若き日の原点に立ち返ろうとしたのだ。
ミケロッティのアトリエから続々と生み出される個人的なワンオフにはG.M.のブランドネームが与えられた。まずはクーペとスパイダー、2台のオスカ。アルファロメオ"ジュリエッタ"のスペシャルで、空力の洗礼を受けた"ゴッチア"。フランスのスペシャリスト"Budot"の機会部分を流用したクーペ。ジャガー"Dタイプ"。そして数多くのワンオフ"スペシャル"フェラーリ。
これらの中でも、"G.M."の名で最後に製作したフェラーリGTB/4については興味深い逸話が残っている。息子のエドゥガルド・ミケロッティが完成させて、その年のトリノ・ショーに出品したのだが、居合わせたフェラーリのインジェニェーレたちは、そのあまりにも低いボンネットラインを見てその下に自分達が製作したV12エンジンが収まっていることを決して信じようとはしなかったというのである。
エドゥガルド・ミケロッティは、父親の死後も数年間は自動車デザインに携わっていたが、後に別の工業製品に興味を移し転向していった。しかし、偉大な父の姿と業績ついては忘れることなく、生き生きとした記憶とともに語ってくれた。
CAR MAGAZINE からの転載
|
|
 |
|
|
|